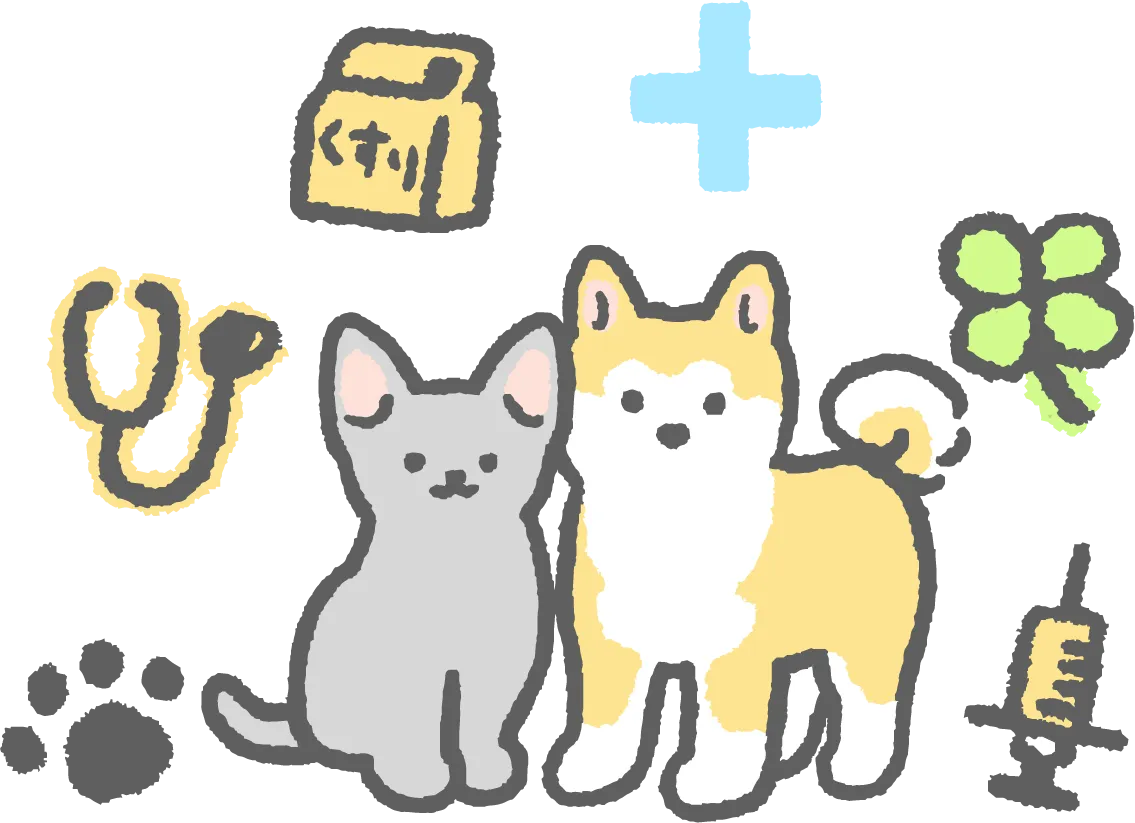「最近うちの猫、よく水を飲むようになったかも…」と感じたことはありませんか?
実は、それは高齢猫に多い腎臓病のサインかもしれません。腎臓病は、腎臓の働きが少しずつ低下し、最終的に体のバランスを崩してしまう進行性の疾患ですが、早期発見と適切な治療によって進行を抑え、長く健康的に過ごすことが可能です。
この記事では、腎臓病の基礎知識や症状、早期発見の重要性、治療・管理法についてわかりやすく解説します。

腎臓病の基礎知識
腎臓は、体の中にたまる老廃物をろ過して尿として排出するほか、水分や電解質(ナトリウムやカリウムなど)のバランスを整え、血圧を適切に保つなど、多くの役割を担っています。腎臓にダメージがあると、不要な物質が体に蓄積してしまい、さまざまな体調不良を起こす原因となります。
〈急性腎臓病と慢性腎臓病の違い〉
腎臓病には大きく分けて「急性腎臓病」と「慢性腎臓病」があります。
・急性腎臓病
中毒や感染症、尿路閉塞などによって、腎臓の働きが短期間で急激に低下する病気です。治療が遅れると命に関わることもあるため、緊急の治療が必要です。
・慢性腎臓病
時間をかけてゆっくり腎機能が落ちていく病気で、高齢の猫に多く見られます。初期の頃は症状がほとんどなく、気づいたときには腎臓の機能がかなり低下しているケースも少なくありません。
なぜ猫は腎臓病になりやすいのか?
猫は砂漠地帯出身の動物で、水分摂取量がもともと少なくても生きていけるように進化してきたと考えられています。
現代の飼育環境では、特にドライフード中心の食生活だと水分量が不足しがちになり、慢性的に脱水状態となることが多いです。こうした状況が腎臓に負担をかけ、加齢とともに腎機能の低下が進行しやすくなります。
慢性腎臓病の進行度(ステージ分類)
進行度に応じて4つのステージに分類(IRIS分類)されます。
| ステージ | 具体的な症状 |
| Ⅰ | 血液検査で異常が出る前の段階で、明らかな症状はほとんどありません。 |
| Ⅱ | 水や尿の量が増え、毛艶が落ちる場合があります。 |
| Ⅲ | 食欲不振、体重減少、嘔吐などの症状が出やすくなります。 |
| Ⅳ | 腎機能が大幅に低下し、貧血や脱水、衰弱などが目立ち、死に至る可能性も高まります。 |
早期ステージのうちに異常を発見できれば、治療で進行を抑えることが可能です。
腎臓病の主な症状
慢性腎臓病は進行性であり、症状が現れる頃には腎機能の低下がかなり進んでいる場合が多いです。飼い主様が日頃からこまめに猫の様子を観察し、小さな変化を見逃さないことが重要です。
〈初期症状〉
・水をよく飲むようになる
・尿量が増える
・毛艶が徐々に悪くなる
・なんとなく元気がない
初期のうちは症状が軽いため、見落としがちですが、この段階で気づければ最も理想的です。
〈中期症状〉
・食欲の低下
・体重の減少
・嘔吐や下痢の頻度が増える
・口臭(アンモニア臭)が強くなる
ここまで進むと、猫自身も体調の悪化を強く感じている可能性が高く、早急な受診が必要です。
〈末期症状〉
・全身の衰弱が進み、ほとんど動かなくなる
・脱水が進み、皮膚の張りが極端に低下する
・尿がほとんど出なくなる(尿閉)
・痙攣や意識障害が現れる
この段階では、延命処置や緩和ケアが中心となります。できるだけ早い段階で治療を開始することが何よりも大切です。
診断方法と検査内容
腎臓病の正確な診断には、複数の検査を組み合わせることが重要です。血液検査や尿検査だけでなく、超音波検査や血圧測定なども行うことで、病気の進行具合や適切な治療方針を決定できます。
〈血液検査〉
血液検査では、腎臓の働きが低下しているかどうかを判断します。特に「クレアチニン(Cre)」や「血中尿素窒素(BUN)」は、腎臓病の指標となる数値です。
また、最近では「SDMA」というより早い段階で腎機能の低下を捉えられる検査もあります。クレアチニン値が正常範囲でも、SDMAの上昇が見られれば早期腎不全の可能性があるため、初期の段階での発見につながります。
〈尿検査〉
血液検査だけでなく、尿検査も腎臓の状態を評価する上で欠かせません。特に以下の点をチェックします。
・尿比重:腎臓が尿を濃縮できなくなると、尿が薄くなります。
・タンパク尿:尿中にタンパクが混ざっている場合、腎臓のダメージが進んでいる可能性があります。
・尿沈渣(にょうちんさ):細菌や結晶の有無を確認し、感染症や尿路結石の可能性を評価します。
〈超音波検査〉
腎臓の大きさや形状、内部構造を確認します。慢性腎臓病が進行すると、腎臓が小さくなったり、表面がでこぼこになったりすることが多いため、診断や進行度の評価に役立ちます。また、腎結石や腫瘍の有無を確認する際にも有効です。
治療方法と管理の仕方
腎臓病の治療は、「腎機能の回復」ではなく、「病気の進行を遅らせる」ことです。進行度や症状に合わせて、次のような治療や管理を行います。
1.食事療法(腎臓病用フード)
腎臓の負担を軽減するには、まず食事の見直しが欠かせません。慢性腎臓病の猫には、タンパク質やリン、ナトリウムの含有量が制限された「腎臓病用フード」が推奨されます。
しかし、腎臓病食に切り替えた途端に食欲が落ちる猫も多いため、徐々に慣らしながら変更することが大切です。
2.点滴治療
慢性腎臓病が進行し、腎臓が老廃物を十分に排出できなくなってくると、体内に毒素が溜まりやすくなります。このようなとき、点滴治療が効果的です。
〈軽度〜中等度の腎臓病の場合〉
定期的な皮下点滴を行うことで、水分とミネラルの補給をしながら、老廃物を体外へ排出しやすくします。通院して行う場合もあれば、獣医師の指導のもと、自宅での皮下補液が可能となるケースもあります。
〈重度の腎臓病の場合〉
さらに重症の場合、静脈点滴(入院)での集中的な治療が必要になることもあります。老廃物や毒素をできるだけ速やかに希釈・排泄し、猫の状態を安定させることが目的です。
日常生活でのケアとサポート
腎臓病の管理には、日々のケアがとても重要です。飼い主様が愛猫の様子をしっかり観察し、食事や水分摂取、生活環境を整えることが、病気の進行を遅らせる大きなポイントになります。
・食事の与え方
食欲が落ちることがあるため、食べやすい形状や温度に調整するのも効果的です。例えば、ウェットフードを温めたり、腎臓病用フードに食欲をそそるトッピングを少量加えたりすることで、食べる意欲を引き出せることがあります。
・水分摂取の工夫
猫が積極的に水を飲めるよう、水の置き場所を増やしたり、飲みやすい容器を用意したりするのも良い方法です。水道水を嫌う猫もいるため、フィルターを通した水や、ミネラル分の少ない軟水を試してみるのもおすすめです。
・ストレス管理の重要性
腎臓病の猫は、ストレスを感じると体調が悪化しやすくなります。静かで落ち着ける場所を用意し、猫が安心して生活できるようにしましょう。
・定期的な通院の必要性
病気の進行状況を確認するために、定期的な血液検査や尿検査を受けることが推奨されます。状態に応じた適切な治療を行うためにも、かかりつけの動物病院と連携しながらケアを続けていきましょう。
まとめ
猫の腎臓病は、一度ダメージが進むと元には戻りません。そのため、早期発見が何より重要です。7歳を過ぎたら年に1回、10歳を超えたら年に2回の定期健診を受け、血液検査や尿検査などを通じて腎臓の状態をこまめにチェックしましょう。
兵庫県神戸市須磨区の『おおした動物病院』
℡:078-731-0001