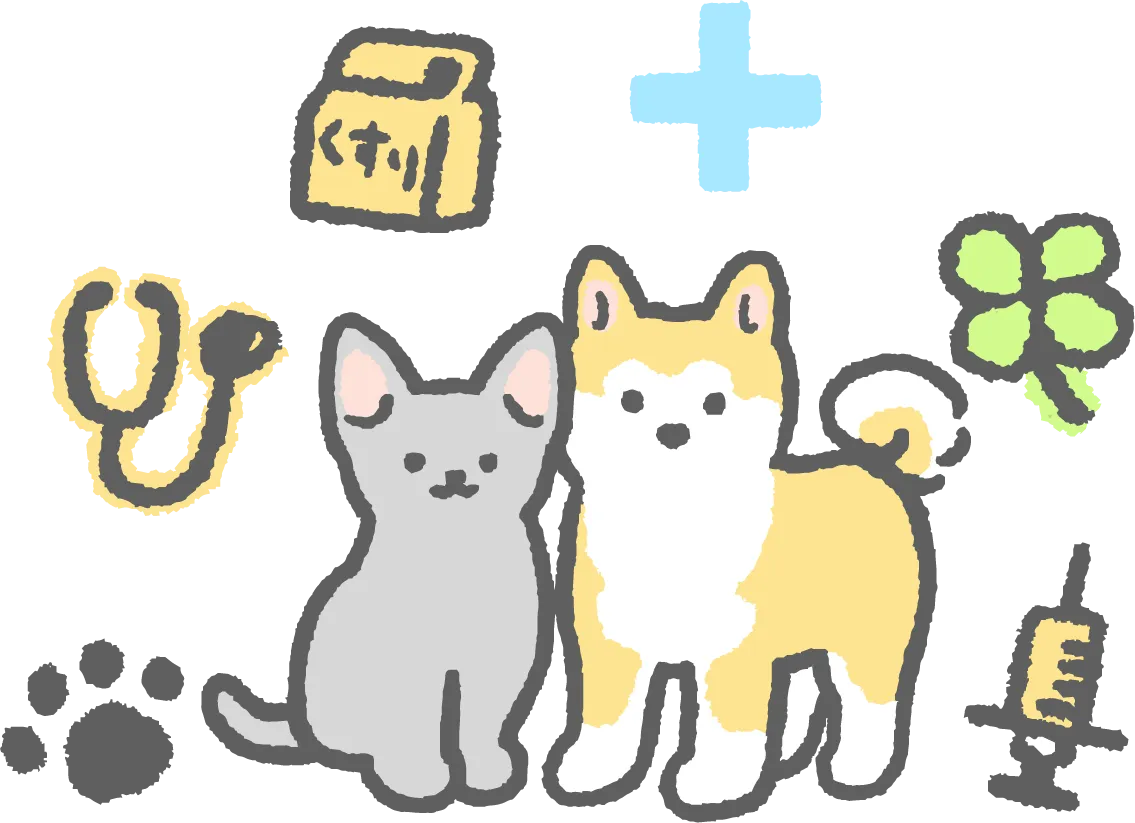犬の腎臓は、体内の老廃物を尿として排出し、体液や電解質のバランスを保つなど、生命維持に欠かせない重要な臓器です。
高齢になるほど腎臓は少しずつ機能が衰えやすくなりますが、若い犬でも不適切な食事や感染症などをきっかけにダメージを受けることがあります。こうしたトラブルが起こると、急性腎臓病として一時的に症状が出る場合もあれば、慢性腎臓病として徐々に進行していくケースもあり、気づいたときには重い状態に陥っていることも少なくありません。
そこでこの記事では、犬の腎臓病がどのように起こり、どんな症状があらわれるのか、そして早期発見・早期対処の重要性や治療・管理のポイントについてわかりやすく解説します。

急性腎臓病と慢性腎臓病の違い
犬の腎臓病には、大きく分けて「急性腎臓病」と「慢性腎臓病」があります。どちらも最終的には腎機能の低下を招きますが、発症の仕方や経過、予後に違いがあります。
〈急性腎臓病とは〉
急性腎臓病は、短期間のうちに急激に腎機能が低下する状態を指します。
原因としては、中毒(不適切な薬剤や有害物質の摂取)、重度の感染症、外傷による大きな出血やショックなどが挙げられます。
急性腎臓病では嘔吐や食欲不振、脱水、元気消失が一気に進行しやすいため、発見が早ければ適切な治療を行うことで腎機能が回復する可能性も十分あります。
しかし、気づくのが遅れると症状が悪化し、致命的な状態に陥ることもあるため、わずかな異変でも動物病院で診察を受けることが大切です。
〈慢性腎臓病とは〉
一方、慢性腎臓病は加齢や遺伝的要因、不適切な食事や長期的な脱水など、さまざまな原因が複合的に重なって少しずつ腎機能が衰えていく病気です。
高齢の犬に多いのが特徴で、初期の段階では症状が非常にわかりにくいため、飼い主様が気づいた時には腎臓がかなりダメージを受けていることも珍しくありません。いったん機能が低下してしまうと元に戻すことは難しいですが、早期に発見し適切な管理や治療を行うことで進行を遅らせ、愛犬がより快適に暮らせる期間を延ばすことが期待できます。
犬の腎臓病の主な症状とサイン
腎臓病のサインは、ごくわずかな日常の変化として表れることがあります。とくに慢性腎臓病の場合、飼い主様が気づけるような症状は「かなり進行してから」出るケースが多いため、日頃から以下のような点を意識して観察することが大切です。
・水を飲む量が増えた、または減った
・おしっこの量(回数)が変わった
・食欲の低下や体重の減少
・毛艶が悪くなり、被毛がパサついている
・なんとなく元気がない、疲れやすそうに見える
腎機能がさらに低下してくると、嘔吐や下痢、口臭(アンモニア臭)、重度の脱水、貧血など、全身的な症状が出ることもあります。これらは必ずしも腎臓病だけに見られる症状ではありませんが、複数の異変が重なるようならできるだけ早く動物病院を受診し、検査を受けることをおすすめします。
腎臓病の診断方法
腎臓病は、定期的な健康診断で早期発見できる場合があります。主な診断方法は以下のとおりです。
1.問診と身体検査
飼い主様からのヒアリングをもとに、普段の食事量や飲水量、尿や便の状態、行動の変化などを詳しく確認します。そのうえで、聴診や触診などの身体検査を行い、脱水や痛みの有無、全身状態をチェックします。
2.血液検査・尿検査
BUN(尿素窒素)やクレアチニン、SDMAなど腎臓に関連する数値を測定し、腎機能がどの程度低下しているかを評価します。尿検査では、尿の比重やタンパク質量、潜血の有無などを調べることで腎臓の濾過機能や尿路系の状態を把握します。
3.超音波検査などの画像診断
腎臓の形状や大きさ、内部構造を観察することで、慢性腎臓病による腎臓の萎縮や、腫瘍・結石の有無なども確認できます。
▼超音波検査について詳しく知りたい方▼
犬猫の超音波検査でわかること | 早期発見のカギとなる精密検査
当院では、高精度の画像診断装置を導入しており、血液検査や尿検査だけではわからない異常を発見できる場合があります。さらに、院長は日本獣医腎泌尿器学会認定医の資格を持っており、腎臓や泌尿器に関する専門的な知識と豊富な経験に基づき、より的確な診断・治療方針をご提案することが可能です。
特に7歳を過ぎたシニア犬には、年に1〜2回の定期健診をおすすめしています。小さな変化を見逃さず、早期に対処していくことが愛犬の健康寿命を延ばすカギとなります。
犬の腎臓病の治療法と管理方法
腎臓病の治療は、残念ながら「完治」を目的とするのではなく「進行を抑え、症状を緩和する」ことが中心となります。以下のような方法を組み合わせて、愛犬の状態をできる限り安定させることを目指します。
・食事療法
腎臓への負担を軽減するため、低タンパク・低リンなど栄養バランスが調整された療法食を与えます。
・薬物療法
高血圧のコントロールや、老廃物の除去を補助する薬が処方される場合があります。吐き気や胃酸過多を抑える薬など、症状に合わせて投薬を行うこともあります。
・輸液(点滴・皮下補液)
脱水や老廃物の排出をサポートするため、動物病院で点滴を行うほか、場合によっては飼い主様が自宅で皮下補液を継続するケースもあります。
日常ケアと予防のポイント
犬の腎臓病は、一度進むと回復が難しいため、日頃のケアがとても大切です。まずは水分をしっかり摂らせる工夫をしましょう。
きれいな水をいつでも飲めるようにしたり、ウェットフードを与えたりすると、腎臓への負担を軽くできます。次に、定期的に健康診断を受けることも重要です。血液検査や尿検査、超音波検査を組み合わせることで、腎臓だけでなくほかの臓器の異常も早めに見つけられます。
また、食事はタンパク質や塩分などをとりすぎないよう気をつけると安心です。獣医師に相談しながら、愛犬に合ったフードを選ぶと良いでしょう。さらに、飲水量やおしっこの回数・量、食欲の変化などを日頃からよく観察しておくと、「なんだかいつもと違う」と思ったときに早く気づけます。こうした小さな心がけが、腎臓病の予防や早期発見につながります。
▼健康診断の重要性について詳しく知りたい方▼
犬と猫の健康診断でわかること | 長寿のための予防医療
まとめ
犬の腎臓病は、気づかないうちに進行していることが多く、症状が出たときにはすでに腎機能が大きく低下していることもあります。だからこそ、日々の小さな変化を見逃さず、定期的な検査を習慣にすることが、愛犬の健康を守る第一歩です。
当院では、最新の検査機器を活用し、早期発見と適切な治療の提供に力を入れております。「最近ちょっと水をよく飲む気がする」「おしっこの量が増えたかも」と感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。飼い主様とともに、愛犬がいつまでも元気に暮らせる毎日をサポートしてまいります。
兵庫県神戸市須磨区の『おおした動物病院』
℡:078-731-0001