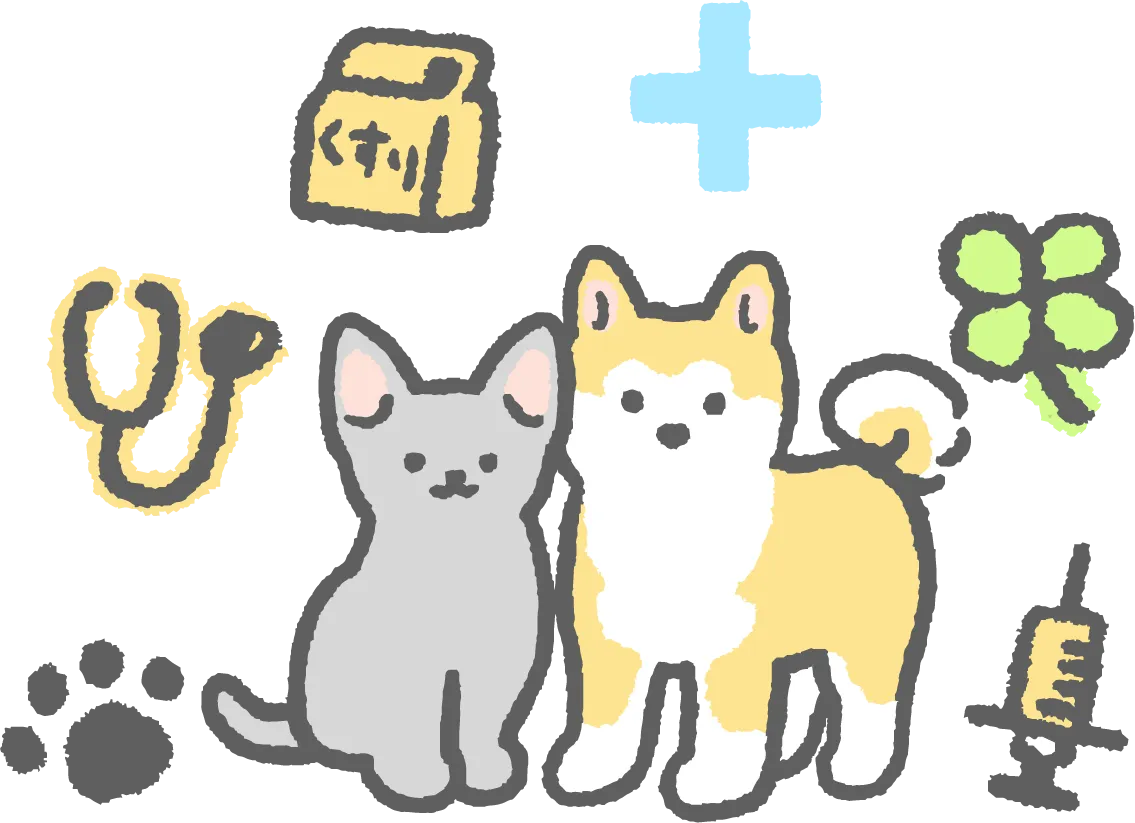「最近トイレに行く回数が多い」「おしっこをするポーズをしているのに、出ていないかも?」そんな些細な変化が、実は重大な病気のサインかもしれません。
猫は痛みを隠してしまうことが多く、飼い主様が異変に気づいたときにはすでに症状が進行していることも珍しくありません。とくに排尿に関わるトラブルは、命に関わるケースもあり、早めの対応がとても大切です。
なかでも「下部尿路疾患」と呼ばれる病気は、猫にとって身近なトラブルの一つです。特にオス猫では尿道閉塞を起こしやすく、排尿ができなくなるとわずか1〜2日で腎不全や尿毒症に進行することもあります。
そこで今回は、猫に多い下部尿路疾患の症状や、緊急性が高いサインの見分け方、さらに再発を防ぐための生活環境の整え方についてご紹介します。

排尿トラブルは猫のSOS|下部尿路疾患ってどんな病気?
下部尿路疾患(FLUTD:Feline Lower Urinary Tract Disease)とは、猫の膀胱や尿道に関係する病気の総称です。人間でいう「膀胱炎」や「尿道炎」「尿路結石」「尿道閉塞」などに相当し、尿を作る腎臓から体外へ排出されるまでの経路のうち、特に下の部分(膀胱〜尿道)にトラブルが起こる状態を指します。
具体的には、以下のような病気が含まれます。
・膀胱炎(細菌性または特発性)
・尿石症(ストルバイト結石、シュウ酸カルシウム結石など)
・尿道閉塞
・尿道の炎症やけいれん
・腫瘍や外傷による排尿障害
なかでも注意が必要なのは、尿道が完全に詰まってしまい、尿がまったく出なくなる「尿道閉塞」です。特にオス猫は尿道が細く、S字に湾曲しているため、メス猫よりも結石や粘液などが詰まりやすい構造をしています。
尿道閉塞が起こると、わずか1〜2日で腎不全や尿毒症を引き起こし、命に関わる事態になりかねません。そのため、早期の受診・対応が極めて重要です。
こんな症状は要注意!すぐに動物病院へ
下部尿路疾患では、以下のような症状が見られることがあります。
・トイレに頻繁に行くが、尿が少量しか出ない
・排尿姿勢をとるが、何も出ない
・排尿時に痛がる素振りを見せたり、鳴いたりする
・尿に血が混じる
・トイレ以外の場所で排尿する
特に「尿が出ていない」状態は緊急性が非常に高いため、すぐに動物病院を受診してください。丸一日排尿していない、あるいはぐったりしている場合は、命に関わる状態です。
また、「排尿の様子が少しおかしいけれど、元気や食欲はあるから大丈夫」と様子を見てしまうのは危険です。猫は不調を隠す傾向があるため、見た目は元気そうでも急激に悪化するケースがあります。少しでも「いつもと違うかも」と感じたら、できるだけ早めにご相談ください。
下部尿路疾患の主な原因とは?
猫の下部尿路疾患は、さまざまな原因で起こります。中には明確な原因がわかるものもあれば、はっきりしないものもあります。ここでは代表的な原因を詳しくご紹介します。
◾️特発性膀胱炎
もっとも多く見られるのが「特発性膀胱炎」です。これは細菌や結石が関与していない、いわば“原因不明”の膀胱炎ですが、実際にはストレスや環境の変化が深く関係していると考えられています。
例えば引っ越しや来客、模様替え、多頭飼育、トイレの場所や砂の変更などがストレスとなり、膀胱に炎症が起こることがあります。
このタイプの膀胱炎は再発を繰り返しやすいため、環境を整えてストレスを減らすことが何より重要です。
◾️細菌性膀胱炎
猫では比較的まれですが、特に高齢の猫や糖尿病・腎疾患などの基礎疾患がある場合は、細菌感染が膀胱炎の原因になることがあります。尿道口から細菌が逆流して膀胱に感染するパターンが多く、抗菌薬での治療が必要です。
◾️尿石症(尿結石)
尿に含まれるミネラル成分が結晶化し、やがて石のような塊になる病気です。代表的な結石には以下の2種類があります。
・ストルバイト結石:マグネシウム・アンモニウム・リンが主成分で比較的溶けやすく、食事療法での管理が有効です。
・シュウ酸カルシウム結石:食事療法では溶解できないため、手術やカテーテルでの対応が必要になることもあります。
これらの結石は、水分摂取量が少ない場合や、ミネラルバランスの偏った食事によって形成されやすくなります。特にドライフード中心の食生活で、水をあまり飲まない猫ちゃんは注意が必要です。
◾️尿道閉塞
上記の特発性膀胱炎や尿結石が進行した結果、尿道が塞がれてしまう状態です。特に細胞や血液が塊となり栓子と呼ばれる「プラグ」が尿道に詰まると、排尿が完全にできなくなり、急激に症状が悪化します。
尿道閉塞は、下部尿路疾患の中でも最も緊急性の高い状態です。
動物病院での検査
猫の下部尿路疾患が疑われる場合、動物病院では次のような流れで診察・治療を行います。
① 問診と身体検査
まず、排尿の様子や症状、食事内容、生活環境について詳しくうかがい、膀胱の張りや腹部の痛みなどを確認します。
② 尿検査
採取した尿から、色・濁り・pH・比重・潜血・結晶・細菌の有無などを調べます。
③ 画像検査(超音波・レントゲン)
膀胱や尿道の状態、結石の有無などを調べます。
超音波検査でわかることや検査の特徴・メリットについてより詳しく知りたい方はこちら
④ 血液検査(必要に応じて)
尿道閉塞など重症例では、腎機能や電解質バランスの異常を調べるために血液検査を行います。
診断後の治療内容
症状に応じて、以下の治療を行います。
〈軽度の場合〉
・内服薬(抗炎症薬や抗菌薬)
・療法食での食事管理
・水分摂取やトイレ環境の見直し
〈尿道閉塞など重度の場合〉
・カテーテルでの導尿と膀胱洗浄
・点滴治療で脱水や電解質異常の改善
・再発防止のための内服薬・療法食の継続
再発しやすいからこそ、生活環境の見直しがカギ
下部尿路疾患は体質による再発のリスクが高いため、再発予防には日常生活の改善が欠かせません。
特に以下のポイントを意識してみてください。
・水分摂取の促進
水をしっかり飲むことで尿が薄まり、結石ができにくくなります。ウェットフードの併用や、複数の場所に清潔な水飲み場を設置することが有効です。
・快適なトイレ環境の整備
猫はトイレに敏感です。常に清潔を保ち、静かな場所に、頭数+1個を目安に設置しましょう。
・ストレスの軽減
来客や模様替えの頻度を控える、落ち着けるスペースをつくるなど、猫が安心して過ごせる環境を整えることも大切です。
・食事管理
結石予防に配慮した療法食やサプリメントを、獣医師の指導のもとで継続的に取り入れると効果的です。
日常の観察と定期健診で、再発を防ごう
普段からおしっこの回数・量・色・においなどに意識を向け、ちょっとした変化にも早く気づけるよう心がけましょう。
また、症状が出ていなくても、半年から1年に一度は尿検査や超音波検査を含む健康診断を受けておくことで、膀胱や尿道の異常を早期に発見できる可能性があります。
過去に下部尿路疾患を起こしたことがある猫はもちろん、まだ症状がない猫でも、予防の観点から定期健診を習慣化することをおすすめします。
大切なのは、「いつも通り」をよく知っておくこと。そして、小さな違和感に気づけるよう、日々の変化を見逃さないことです。飼い主様の気づきが、再発の予防にもつながります。
犬と猫の健康診断でわかることについてより詳しく知りたい方はこちら
まとめ
猫の排尿トラブルは、元気そうに見えても命に関わることがあり、決して軽視できません。また、一度発症すると再発しやすいという特徴もあります。
日常の観察に加えて、生活環境の見直しや定期的な健康チェックを習慣にすることが、愛猫の健康を守る第一歩です。
おおした動物病院では、腎泌尿器疾患に詳しい獣医師が、丁寧に診察・アドバイスを行っています。気になる症状がある方、生活環境についてご相談がある方は、どうぞお気軽にお声かけください。
兵庫県神戸市須磨区の『おおした動物病院』
℡:078-731-0001